僕は中1で、「あさがお」という合唱曲をクラスで歌うことになりました。しかし、最後の方のゆっくりになるところのリズムが取りづらく難しいです。何かコツなどを教えていただくと嬉しいです。
こちらの質問にお答えしていきますね。
質問内容の確認
最初に、質問内容を明確にしたいと思います。
質問中の「最後の方のゆっくりになるところ」とは、具体的には【51小節以降】でよろしいでしょうか。
こちらの動画でいうところの 3:26 辺りです。
https://www.youtube.com/watch?v=O8WMi8QW1o4
51小節でrit. がかかり、52小節以降はmeno mosso でゆったりとしたテンポになります。
以下のアドバイスは、質問が上記箇所であるという前提の下で書いていきます。
もしてんで違う箇所について話していたら、指摘してください。
質問への回答
まずはこちら。
「ゆっくりになるところのリズムが取りづらく難しい」
これについては↓のような手順で取り組むことを提案します。
【手順】
- ピアノ伴奏を含め、理想の状態が自分の頭の中にあるかを確認
- 1の理想の状態に合わせて指揮を振る練習をする
- 1の理想の状態を合唱団と共有し、全体練習で調整する
この流れです。
最も重要なのは
最重要なのが1番目の「ピアノ伴奏を含め、理想の状態が自分の頭の中にあるかを確認」です。
もう少し別の言い方をすると、
「理想の状態を鼻歌とかで歌えますか?」
とかになります。
「自分はこの部分をこういう風に演奏したいんだ」という状態を鼻歌でいいので歌えますか?と。
これ、指揮者をやるんでしたら出来て当然なことなのですが、意外と出来ない人が多いんです。
理想の状態が指揮者の中にない。
理想の状態が決まってないから音楽づくりの方向性も決まらないし、当然、指揮(腕での振り方)も決まらない。
ですから最初に取り組むべきは、自分の中に「理想の状態」を作ることです。
理想の状態を決める際に考えること
本当はここで、曲に関する色んなことを考慮すべきなのですが…
クラス合唱でしたら、まずは「理想のテンポ・リズム」を決めるようにしましょう。
「こんな感じのテンポ感で演奏したいんだよね」
「給付はこのくらいの長さにしたいんだよね」
こんな風に。
そしてそれらが決まったら、
「この部分はどんな風に演奏したら、楽曲の良さを引き出せるかな」
みたいなことを考えてみましょう。
そうすると必然的に、曲の雰囲気が決まってきます。
明るいのか暗いのか。
強いのか弱いのか。
真剣な顔なのか優しい顔なのか。
緊張しているのかリラックスしているのか。
などなど。
こんな風に曲の雰囲気が決まると、当然に指揮の方向性も決まってきます。
腕の振り方によって↑の雰囲気を表現するわけですから。
とまあこのように「自分がどんな曲にしたいか」を決め、それを深掘りしていくことで、ある程度は指揮の振り方の方向性が決まります。
まずはこのようなプロセスを踏んでみてください。
上記アドバイスをさらに別角度から
で、あと指揮及び演奏のコツについても少し書いておきます。
質問対象である【51小節以降】の指揮と演奏のちょっとしたアドバイスです。
そのアドバイスとは、
歌詞を聴かせる演奏(指揮)をする
です。
歌詞の意味
例えばですが。
52~53小節にかけて、「まっすぐ」という歌詞が2回繰り返されますね。
meno mosso で全パート同じ音の動きになるところです。
この2回繰り返される「まっすぐ」という歌詞、どう演奏したらよいと思いますか?
あるいは、以下のように言い換えても構いません。
『あさがお』という楽曲において、この「まっすぐ」が2回繰り返される部分はどのような役割を持っていると思いますか?
あるいは、
作曲者は「まっすぐ」を2回繰り返すことで何を表したかったのでしょうか?
こんな風に自分に問いかけてみてください。
そしてそれらの答えが決まったら、さらに以下の問いに答えてみてください。
これら質問への回答を踏まえ、あなたはこの「まっすぐ」の繰り返しをどのように演奏したいですか?
どのような情景を思い浮かべ、どんな気持ちで合唱団に歌ってもらい、それを聞いたお客にどんな感情を抱いて欲しいですか?
歌詞を表現するための腕の振り方
これら問への答えが決定すると、指揮の振り方の方向性が決まります。
・大きく振るのか小さく振るのか
・激しく振るのか優しく振るのか
・固く振るのか柔らかく振るのか
・指揮を振る高さはどのくらいがよいか
など。
あとは腕以外にも
・表情はどんな感じがよいか?
・胸の開き方はどのくらいがよいか?
なども。
こういうことを、”鏡を見て実際に腕を振りながら”考えていきます。
そうすると、
「繊細な雰囲気を出したいのに、自分のこの振り方じゃガサツな見え方になるな」とか
「2回目のまっすぐをより印象付けたいのに、今の振り方じゃ1回目と違いが見えないな」とか
自分の指揮を自分で作っていけるようになります。
もしこのレベルで自分の指揮を作れるようになったら最強です。
人に聞かなくても、自分で指揮を作っていけるんですもん。
他の部分でも同じように考える
今回は「まっすぐ」を例に出しましたが、楽曲の他の部分でも同じように考えてみてください。
他のクラスの指揮者が「ただ何となく指揮者っぽい動きをしているだけ」のに対して、
あなただけ「圧倒的な情報量を持った、考え抜かれた腕の動き」をすることになりますから。
まぁ指揮のことを分かっていない人からしたら、それっぽい動きをしている指揮者を評価することがあるかもしれませんが、
多少そういった心得のある人から見たら「あのクラスの指揮者だけレベル違うんだけど。すご。」ってなります。
絶対後者の方が楽しいですよね(笑)
ということで、以上が私からの返信です。
より詳細な指揮の振り方も紹介できなくもないのですが、文字だとまぁまず正しく伝わらないと思いまして。
今回のような、どうしたら生徒が自分で指揮を作り上げられるか?の視点でアドバイスを書いてみました。
もし、さらに詳細なアドバイスを希望する場合、ご自身が指揮を振っているところを動画で送っていただければ、より細かくアドバイスすることも可能です。
よろしければご検討くださいませ。
それでは。
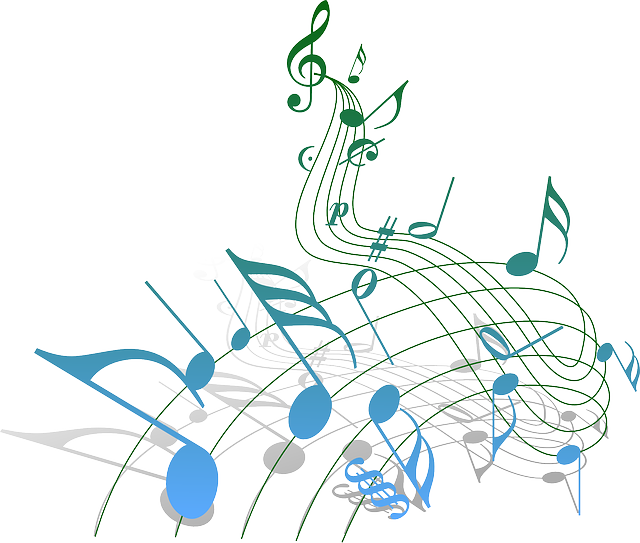
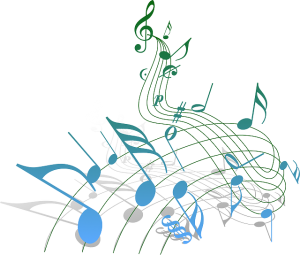
コメント
コメント一覧 (1件)
記事を書いていただき、ありがとうございます。とても分かりやすかったです。これらのことを意識して、オーディションで合格できるように頑張ります!