元の質問
中学校の合唱コンクールで「空駆ける天馬」の指揮をします。
テンポが変わるタイミングの指揮が難しくて、指揮者なのにリズムが狂ってしまいます。
正確にしなければいけないのはわかっているのですが、伴奏も一度途切れるところなので目印(?)も無くて、できません…。
何か良い方法は無いでしょうか?
質問への回答
質問箇所の確認
まず確認させてください。
“テンポが変わるタイミング”というのは、今回の『空駆ける天馬』の「静まりかえる」の部分でしょうか?
「風さえのけぞる」の後、小節数で言うと27小節から。
今回のお返事は上記の箇所であるという仮定の下で進めていきますね。
一応、以下に2つの対策を書き出しました。
ですが正直、1つ目の対策でことは足りるのではと思っています。
だから2つ目はおまけみたいなものです、1つ目が上手くいかなかったときに使ってください。
対策1:自分で歌いながら指揮を振る練習
どのパートでもいいので、まずは自分で該当箇所を歌ってみましょう。
すると、質問者さんが「こうしたい」と思うテンポが見つかると思います。
そのテンポを指揮で表現できるよう練習します。
もし「こうしたい」と思うテンポが浮かんでこなければ、それは指揮者として不適格です。
指揮の振り方云々以前に、どういう音楽を作りたいのかを決めるのが先です。
楽譜とにらめっこするもよし、合唱団と話し合うもよし、他の音源を聞くのもよし。
とにかく楽曲と向き合って、自分の中に「この曲のこの部分はこうしたいんだよね!」という感覚を育てましょう。
対策2:他の音源を参考に指揮を振る練習
「こうしたい」と思うテンポが浮かんでこない場合の補助策のようなものです。
Youtubeなどで音源を探し、それを参考に指揮を振る練習をします。
指揮者が映っている動画だと真似しやすいかもしれませんね。
ただ、やっぱりこれは補助的な対応です。
他の音源を参考にし過ぎると、目の前の合唱を素直に聞けなくなるからです。
ですから1番はやっぱり、自分の中に「こういうテンポ感がいい!」という感覚を育て、それを指揮で表現できることです。
補足:ritのタイミング
質問者さんの質問箇所が「静まりかえる」の部分であるという前提の下、最後に1点だけ補足しておきます。
ritをかけるタイミングです。
楽譜を見ると、28小節目からritがかかっていますが、26小節2拍目辺りから徐々にかけ始めるといいかもしれません。
「風さえのけぞる」の「る」の音を4拍伸ばしますよね。
この4拍伸ばす音の2拍目辺りから、少しずつritをかけるんです。
こうすることによって「静まり」の雰囲気も出しやすくなるし、合唱団もテンポ変化についてきやすいはずです。
もちろんピアノ伴奏も。
補足:指揮は小さく
さらにおまけです。
この楽曲は全体的にテンポが速いため、指揮はそんなに大きく振らない方がいいです。
ベースとなるmfのサイズをやや小ぶりにして、小回りの利きやすい指揮にする感じです。
こうすることで速いテンポでも振りやすくなりますし、なにより合唱団から見て、視覚的なうるささが減ります。
文字だけだと何を言っているのか分からないかもしれませんが、まぁおまけです。
感想をお願いします
以上が私からの返信です。
こちらをお読みになったら、最後に感想コメントをお願いします。
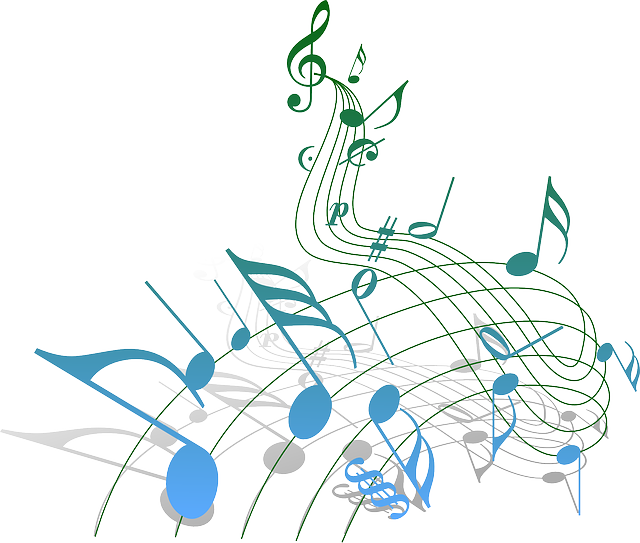
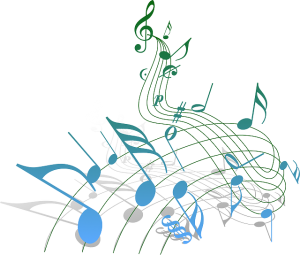
コメント