合唱曲『リフレイン』について、メールにて質問をいただきました。
質問内容はこちらです。
もう少しで合唱コンクールがあり、リフレインの指揮を振ります。
8分の6拍子で、2拍子の図形や三拍子の図形、時計回りで円を描くように振ったりなど色々な振り方があると思いますがどのように振り分ければよいのでしょうか。
また、最後(テノールがこのときはと入ってくるところから)はどのように振ると分かりやすい指揮になりますか?
他にもここの部分はこう振ると分かりやすい・かっこいいなどありましたら教えていただきたいです。
指揮の経験はあまりないですが指揮者賞を取りたいのです。質問が多くて申し訳ありません。回答お待ちしております。
以下、私が質問者さんに返信した内容をシェアします。
※読みやすいよう、こちらのサイトでは見出しを付けてあります
==ここから==
●●さん
指揮法サイトのあさぺんです。
この度はご連絡いただきありがとうございました。
いただいた質問に、出来る限り分かりやすくお返事していきますね。
どうぞよろしくお願いします。
リフレインの楽曲分析
さて、『リフレイン』という楽曲、様々な音源を参考にしながら分析してみました。
私はこの曲を演奏した経験がないのですが、大変難しい楽曲だと感じました。
何が難しいと感じたか。
ズバリ拍子とテンポです。
6/8拍子と、あのゆっくりとしたテンポ。
この組み合わせが非常に難しい。
拍子とテンポ
これは私の感覚なのですが、6/8というのは、音楽が停滞しやすい拍子なんです。
もっさりとしやすいと言ってもいいです。
音楽が前に進みにくい。
だから指揮を振っていて「重く」なりがちです。
そしてその重さは、まずは歌い手を苦しめ、そして聞き手に飽きやくどさを与えます。
ですから、6/8拍子を振るときはなるべくサクサクと音楽を前に進めていきたい。
のですが。
それを難しくしているのが、『リフレイン』のゆったりとしたテンポです。
楽曲のテンポ指定がいくつか分かりませんが、8分音符3つで36前後といったところでしょうか?
これは”超ゆっくりなテンポ”というわけでもないのですが、それでももっさりとしやすいテンポなんですね。
ですから指揮を振る際は、常に
「音楽を前に前に進める」
という意識を持てるといいです。
そうすると指揮が振りやすくなります。
指揮者だけでなく、歌い手も歌いやすくなります。
そして何より、聞き手が『リフレイン』の持つ、爽やかさや甘酸っぱさのようなものを存分に堪能することができます。
音楽がもっさりしてると、繰り返される「くりかえし」の歌詞がくどくなってきます(笑)
以上が、ざっくりとではありますが、指揮を振る上で大前提となる話でした。
「音楽を前に進める」とは
※ちなみに。
誤解を生んでいるといけないので書いておきますが、「音楽を前に進める」というのは「テンポを無視して先走る」こととは明確に違います。
例えば。
「くりかえし」という歌詞を歌うときに、「く(KU)」のK子音を拍のちょっと先に出し、拍を打つ瞬間にはU母音がしっかりとなっている状態を作る、とかです。
上記のようなことを意識して演奏できると、テンポ通りに歌が進みます。
「当たり前のことじゃないの?」と思うかもしれまえせんね。
ですが、これは”当たり前に”出来ることではありません。
日々歌の練習をしている合唱部の人間とかでも、拍に対して言葉が遅れるなんて日常茶飯事です。
ましてやクラス合唱なんて…という感じです。
そして今回の楽曲『リフレイン』には、
「くりかえし」
「来る」
といった「く(KU)」から始まる言葉が何度も何度も出てきます。
ですから、これら言葉を上手に歌いこなせるようになれば、少しずつ音楽を前に前にと進められるようになります。
もちろん、ここで紹介した「く(KU)」の話はほんの一例に過ぎませんので、ああそうなんだ、くらいに思っていただければと思います。
※参考
以下の説明でもたびたび出てきますが、一応オススメ?の音源を載せておきます。
“Youtubeにある中では”、いちばん上手な演奏かと思います。
私としては気になる箇所がたくさんありますが、参考音源として紹介しておきます。
リフレインの指揮の振り方
さて、前置きが大変長くなりました。
ここからが指揮の話です。
いただいた質問に回答していきます。
8分の6拍子で、2拍子の図形や三拍子の図形、時計回りで円を描くように振ったりなど色々な振り方があると思いますがどのように振り分ければよいのでしょうか。
基本は2拍子
この楽曲は基本的に2拍子の振り方でいいと思います。
8分音符3つを1拍と捉え、1小節内の1拍目と4拍目で打点を打つイメージ。
123 456
↑ ↑
(上記の簡易図の↑印のところが打点)
要所で3拍子
曲の後半、ソプラノがソロで「くりかえし歌う鳥」と歌うところなんかは、3拍子×2の振り方をするのもいいですね。
8分音符を1つずつ振り、「123」で3拍子、「456」で3拍子を振る感じです。
123 456
↑↑↑ ↑↑↑
ソプラノが入る半小節前から3拍子でカウントしてあげると、ソプラノが歌いやすいと思います。
この動画の3:03~3:05のところですね
https://youtu.be/rXoKO2l1wVc?feature=shared
テノールソロの入りも3拍子がいいかも
質問にあったテノールソロの入りについても、上記のように振ってあげると分かりやすいです。
ちょうど先の動画の4:13~4:15のところ。
都合の良いことに、動画内の指揮者も私がオススメしている振り方をしていました。
イメージを掴むうえで参考になると思います。
紹介した動画の注意点
ただですね。
特にテノールの入りの部分について、動画内の指揮者の振り方は大きすぎます。
あんなに大きく振ると、歌い手の声も自然と大きくなり、曲が表現したいであろう繊細な雰囲気が崩れてしまいます。
ですから、ソプラノソロの入りにしても、テノールソロの入りにしても、3拍子で振る場合は気持ち小さめで指揮してあげると良いです。
(その方が指揮も振りやすいはずです。腕を動かす距離が短いので。)
指揮の軌道
あと、話が前後して申し訳ないのですが、先ほど以下のように書きましたよね。
「この楽曲は基本的に2拍子の振り方でいいと思います。
8分音符3つを1拍と捉え、1小節内の1拍目と4拍目で打点を打つイメージ。」
このときの2拍子は、楕円の軌道を意識するといいです。
そうすると指揮に丸みが出て、歌にも柔軟性が出ます。
楕円は縦長だったり横長だったり、曲の雰囲気に合わせて調整してください。
楕円のサイズもです。
強拍と弱拍の変化
さらに上記に加えて。
123 456
↑ ↑
この図の「123」で描く楕円は、「456」の楕円よりも大きくていいです。
…ああ、これだと意識が逆ですね。
「456」の楕円は「123」より小さい方がいい、です。
「くりかーえしー」のフレーズを当てはめて考えていただければ、何となくイメージ出来るんじゃないかなと思います。
その他質問への回答
他にもここの部分はこう振ると分かりやすい・かっこいいなどありましたら教えていただきたいです。
まずは立ち姿から
指揮法サイトの諸々の記事はご覧になっていただけましたでしょうか?
そこに書かれていた
・立ち方
・胸の空間
・アイコンタクト
・無音と集中
辺りをまずは意識してみて下さい。
全て曲を振り始める前の話です
「いやそれ指揮の話じゃないじゃーん!」
って思うかもしれませんが、仮にこれらを私と同じレベルで行えたら。
もうそれだけで審査員鳥肌立ちますよ(笑)
もし私がカノンさんの代わりに指揮台に立てるなら、曲を振り始める前の段階で、会場にいる全員の意識を集める自信あります。
そんな状態で演奏が始まったらどうですか?
「この指揮者、他となんか違う…」
ってなりますよね?
ですから、先ほど紹介したようなことをまずは意識してみてください。
その他1:振り過ぎない
で、あと「こう振ると分かりやすい・かっこいい」について。
これは正直、オンライン通話とか動画とかでないと非常にお伝えしづらいのですが…
強いて言うなら「振り過ぎない」ことです。
例えば先にご紹介したこちらの動画。
https://youtu.be/rXoKO2l1wVc?feature=shared
こちらの3:10前後を見てください。
ソプラノソロが静謐に「くりかえし歌う鳥」と歌っているわけですが、指揮者はどんな指揮を振っていますか?
手がブンブン動いてますよね。
曲の雰囲気と合ってますか?って話なんですよ。
ソプラノの静かで繊細な感じと指揮者の腕の動きの雰囲気、合致してますかって。
してないですよね。
ですからこういうところは、腕はほとんど動かさなくていいんです。
ほんのちょっと。
2cmとかそのくらい。
ちょっと動いていることが分かればいいんです。
あとは指揮者の表情で持っていけます。
その他2:ここぞというところで
で、そのあとです。
ソプラノに他パートが合流しますよね。
アルトが加わり、男性も加わり、少しずつ楽曲のうねりみたいなものが大きくなってきます。
そして「くりかえし好きと言う」から「明くる日も」にかけてものすごい盛り上がりますよね。
ここ!
ここでガツンと振る。
先の動画の3:36辺りの指揮者の振り方は1つ参考になるかもしれません(相変わらず拍がうるさいですが)。
空を仰ぐような振り方です。
ここなら、こういう振り方もアリだなって思います。
で・す・が。
先ほども書いた通り、盛り上がりでガツンと振るためには、それ以外の部分で「振り過ぎない」ことが大事なんです。
無駄に大きく振らないとか、
無駄に拍を打たないとか。
そういう無駄を省いて、本当に必要なところだけガツンと振れるようになると、歌い手にも聞き手にも響く指揮ができるはずです。
終わりに
以上です。
頑張って書いてみましたがいかがでしたか?
文字だらけで正直イメージ湧きにくかったと思いますが、何か参考になれば幸いです。
もう何十回&様々な音源を聞きましたから、『リフレイン』という楽曲のイメージは私の中で大分固まっています。
こういう風な曲作りをすればおもしろいだろうなとか、ここはこういう風に振ったら楽しいだろうなとか。
ですから、もしまだ質問があれば気兼ねなくご連絡ください。
時間制限はありますが、Zoomなどで直接指導することも出来ますので。
それでは、●●さんの指揮が上手くいくことを願っています。
==ここまで==
やはり文字で指揮の説明をするのは難しいですね。
というかたぶん、私の言いたいようには伝わっていない(笑)
それでも、質問いただければできる限り真摯に対応しますので。
これを読んでいるあなたも良ければメール送ってみてください。
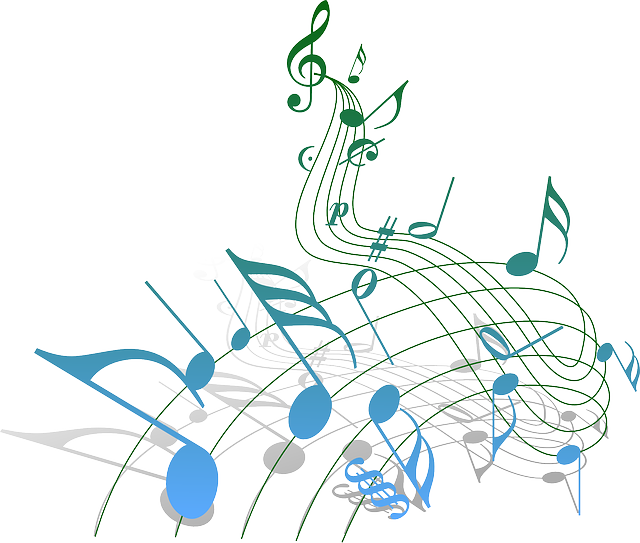
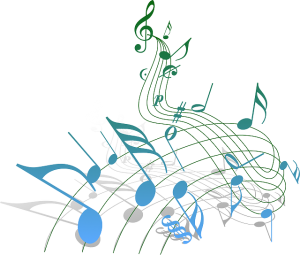
コメント